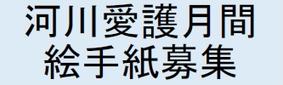エッセー
「ポンプ」と「風土工学」
-英語と日本語、その表記法を考える-
竹林 征三(たけばやし せいぞう)
富士常葉大学 環境防災学部 教授
工学博士
附属風土工学研究所 所長
〔1〕はじめに
ポンプにかかわる協会から何でも良いから随想を書け、できればポンプと関係するものがありがたい、とのことである。
何を書こうか、思い悩んだ。何でも良いと言われるのが一番困る。
そんな時、一番手っ取り早いのが言葉の語源である。依頼があったところがポンプ協会、私が展開しているのが風土工学ということで、ポンプはどう見ても外来語、しからば外来語の語源はどういうことなのだろうか。そして、反対に風土工学は日本で生まれた工学体系、英語でどのように表記すればよいのであろうか。英語と日本語、その語源に逆のぼって、それぞれの表記法について比較考察を進めてみよう。
〔2〕ポンプの語源を訪ねる。どう表記すれば良いか。
ポンプとは何か、英語のpumpの片仮名表記である。Pumpは、圧力の働きによって流体を送る装置であり、現在の都市化社会において、大変お世話になっている、なくてはならぬ文明の利器である。
ところで、ポンプがpumpで短靴パンプスがpumpsで、カボチャがpumpkinである。何故、似ても似つかぬものが同じpumpと記すのだろうか。まず、pumpの語源を訪ねてみよう。16世紀以前の中世代の英語では、pumpeとか、pompeとかと記されていた。中世代のオランダ語ではpompe、スペイン語やポルトガル語ではbomba、ドイツ語ではpumpeであり、フランス語ではpompeである。これらは全て、ポンプで水を吸い上げる時の音からきた擬音語である。
ところで、同じスペルのpumpsパンプス、いわゆるひもや留め金がなく甲皮を深くえぐった靴は、どうしてpumpなのであろうか。この靴は、古くはpoumpeとかpompe、pumpeと記され、ポンプと同じ歴史を持つ。流体ポンプと靴のパンプスは、歴史的にも切っても切れない仲のようだ。姿と形も用途も全く異なるものが、何故に、同じ語源を持つのだろうか。
第1説は、足裏にぴったりしていることを表すために、ポンプのピストン部分を戯語的に適用していたのではなかろうかという説である。第2説は、水につかると水を吸い上げることからという説。さらに第3説はドイツ語のPumpstiefel深靴との関係があるのではという説もある。
私はやはり第1説が一番素直に思えるのだが、どうだろうか。
ところで、カボチャのことをpumpkinという。なぜなのであろうか。kinは接尾語で「…の小さいもの」という意であるが、カボチャは「ポンプの小さいもの」という意になる。どうして姿形が似ても似つかないカボチャがポンプなのであろうか。
カボチャはラテン語でpepon、ギリシャ語でpepon large melon、フランス語でpompon melonである。また、シェークスピアの文にpumpionの形が見られる。これはギリシャ語の原義は熟さないと食べられないところから、「大男」を軽蔑的にいったものだという。
なるほど熟してポンポンという音からの擬音語からカボチャがPumpkinとなったのか、ポンプと短靴、そしてカボチャの深い縁起も解明きれてきた。
ところで、漢字でポンプのことは「喞筒」と書く。「喞」は漢音でショク、呉音でソクで①小さい声が多く集まってうるさいこと、②ひそひそ声、またはなげく声から、③水をそそぐ音という意である。従って、喞喞(しょくしょく)とは、①機を織る小さな音のしきりに聞こえているさま、②虫のしきりに鳴く声、③鳥のしきりに鳴く声、④ネズミの声、⑤小さな嘆息の声ということになる。
このようなことから、ポンプのことをそのような音の出る筒ということから、喞筒(ソクトウ)という。なるほどうまく表したものである。西洋の擬音語ポンプが、漢字文化となると擬音と共に姿形もイメージされてくる。漢字文化の奥深さを感じる。ところで日本語は外来語をそのまま片仮名表記でポンプと記す。日本語の表記法は漢字もアルファベットも、そのまま記すことが出来るし、又、外来語として片仮名で平仮名文章の中に素直に記すことが出来る、実に包容力のある日本語文化の素晴らしさに深く感じ入るばかりである。
〔3〕風土とは何か
私は従来の公共事業の反省に立ち、今後望まれる公共土木事業の工学的実学として、新しく風土工学という体系を構築し、その展開を図ってきている。
風土工学と称する限り、風土とは何かを明確にしなければならない。藤堂明保の「漢和大辞典」(学習研究社)によれば、風土とは「その地方の気候・地形・地味などのありさま。また、土地がら」とある。非常に簡単明瞭である。
風土の用語を用いる限り、和辻哲郎の名著「風土」の解釈を避けては通れない。和辻哲郎は、人間の環境としての自然を「自然」として問題にせず、「風土」として考察しようとすることには相当な理由があるとし、人間存在の構造契機としての風土性を明らかにするとし、風土的形象を自然環境としてではなく、主体的な人間存在の表現として見る立場から
「風土とは土地の気候・地質・地味・景観などの総称であり、人間の環境としての自然を地水火風として把撞した古代の自然観がこれらの概念の背後に潜んでいる。…略…。我々は風土の諸現象において我々自身を見、その自己了解において我々自身の自由なる形成に向かう。…略…。」
すなわち風土の現象を「文芸、美術、宗教、風習等あらゆる人間生活の表現の中に見出す」と述べている。
さらに、和辻哲郎は、人間存在の構造は三つの超越から成り立つと分析している。すなわち、第一超越は“他人において自己を見出す”という社会的構造、第二超越は“歴史において己を見出す”という時間的構造、第三超越は“風土において己を見出す”という空間的構造であるとし、人間の存在構造としての超越は、共同体の形成の仕方、意識の仕方、したがって言語の作り方、さらには生産の仕方や、家屋の作り方などにおいて現れてくる、何々の「ための連関」であるところに道具の本質的な構造があり、「ための連関」を開始せしめる根元に人間存在の風土的規定を見出す、としている。
そこで、筆者なりに風土のやさしい解釈を試みる。風土は「風」と「土」である。風は「漢和大辞典」によれば、
①ゆれ動く空気の流れ。八風(季節ごとのかぜ)
②ゆれる世の中の動き。風潮
③姿や人柄から発して人心を動かすもの。風采、風格
④そこはかとなくただようおもむき。けしき。ほのかなあじわい。風光、風味
⑤ゆかしいおもむき。流風余韻、風雅、風流
⑥大気の動き。気温・気圧などの急変によっておこる病気。風邪
⑦ショックによって気のふれる病気
⑧歌ごえ。民謡ふうの歌。転じて、おくにぶり。ある地方のならわし
(注)詩経では風・雅・頌の三種に詩を分け、風は各地の民謡、雅は都びとの歌、頌は祭礼の時、祖先の徳をたたえる歌、をいう。
動詞として、
⑨かぜに吹かれる
⑩かぜが物を動かすように、ことばで人の心をゆり動かす
⑪動物が発情する。さかりがつく
とある。また、土はその地域という意味であろう。
風土とは、地域の持つ①-⑪までの概念ということになる。しかし、風の物理的概念、つまり英語のwind(そよ風)、breeze(すきま風)、draught(一陣の風)、storm(暴風)などに相当する①、⑨、それにその延長線上の②と、風邪のcold、influenza、その延長線上に相当する⑥、⑦、⑪を除いたものが風土の概念ではなかろうか。すなわち、風土の風とは、
③地域の人々の“姿や人柄から発して人心を動かすもの”:地域の人々の持つ性格の特色
④地域の持つ“そこはかとなく、ただようおもむき、けしき、ほのかなあじわい”:地域の持つ自然環境のうち、感性の訴える深みのあるもの
⑤地域の持つ“ゆかしいおもむき”:地域の持つ社会(社会文化)環境のうち、感性に訴える深みのあるもの
⑧地域の持つ“おくにぶり。ならわし”:地域の持つ歴史環境のうち、感性に訴える深みのあるもの(歴史文化)、伝統行事など
⑩地域の持つ“ことばで人の心をゆり動かす”:地域の持つ言語社会のうち、感性に訴える深みのあるもの(方言、歴史地名、枕詞、地域のイメージキャッチフレーズ・キーワードなど)ということになる。
筆者は、風土とは、“地域の持つ固有の自然環境、社会歴史文化環境、言語文化、人間性のうち人々の感性に訴える深みのあるもの、と定義することとする。
〔4〕感性工学と風土工学
風土工学を新しい学問体系として考える場合、英語での表現が一大問題となる。
風土工学は感性工学の方法論を土木工学にとり入れた実学である。まず感性工学は英語でどのように表示すればよいのであろう。感性工学と風土工学も日本で産まれた新しい工学体系である。
感性工学は、当初、情緒工学と称していたが、情緒は英語ではEmotionとかSentimentとなり、感情的色合いが強くなる。感情的工学ではどうも意味するところが異なる。Atmosphereとすれば、情趣という色合いが出てくる。Atmosphere Technologyでは、空気工学的な意味合いになり、どうもしっくりこない。情緒工学は、日本語のイメージからは、曖昧工学、フアジー工学的イメージがあってもよさそうに思えるのであるが、もうひとつしっくりこない。感性工学の創始者長町三生先生は、そのようなことより感性工学と名前を変えられたのであろうか。
感性は、英語の辞書によるとSensitivityとかSensibilityになる。しかしSensitivity Technologyでは感度工学のようにとられて、電気工学の感度分析のようなイメージとなってしまう。どうもうまくない。
そのようなことで、長町三生先生はKansei Technologyと訳されていると、筆者は憶測している。日本で生まれ育った工学であるので、何も既にある英語を使わず、Kansei Technologyの方が正解であろうと思われるし、筆者も大賛成である。
では、風土工学はどう英訳すればよいのか。風土は、英語の辞書によるとClimateとある。風土学は、Climatologyとなる。すると風土工学は、Climate TechnologyかClimatology Engineeringということになる。Climate Technologyとすれば、どうしても気候工学という意味になってしまう。
Climatology Engineeringとしても、気候学的な工学というような意味になってしまう。どうしてもClimateの気候の概念が強すぎてしまう。筆者が考えている風土工学のイメージからはほど遠い。どのように訳せばよいか。
Cultural Climatology Engineering
これならClimatology内の気候的ニュアンスが若干薄まり、文化的イメージが強く現れてくる。しかし、英語圏の人に風土工学の概念を広めようとすれば、やはりあまりよい名称ではなさそうである。
Cultural Environment Technologyの方がより英語圏の人々にも理解してもらえるかもしれない。しかし、日本語の風土という言葉の持つ奥深い感性に訴える概念は消えてしまう。思い切って、Fuudo Technologyの方が良いのかもしれない。
Fuudo Technologyでは、英語圏の人々には理解してもらうには時間がかかる。もう、少し良い表現はないものであろうか。
Cultural Acclimatology Engineering
すなわち、
Acclimate Public Work to Local Cultural Environment
あるいは、
Acclimate Public Work to Local Identities
ということである。
適切な定義、適切な命名、そしてその適切な英訳は、その概念、そして、その学問としての将来の発展を大きく左右する非常に重要なことである。あえて紙数をさいて論じたものである。
風土工学という言葉は、工学関係者には非常に違和感を与える。なぜなら風土という言葉がかもし出す自己内面的で精神的なものや、文化的なもの、歴史的なものは、今まで工学の対象としては一番遠い対象であったからである。そういうことで風土工学という名称が我が国の工学関係者に馴じむためには若干いや相当に抵抗があるかもしれない。そのような意味では、Cultural Environment Technologyを日本語訳にした文化環境工学の方が、日本国内でもより馴じみが早いかもしれない。いや、やはり、風土という言葉の持つ奥深い概念が伝わってこない。Fuudo Technologyでなければならない。さらに欲をいえば「“風土”Technology」と記すことはできないものであろうか。表音文字による表記法に、表意文字の深い概念を込めることは非常に困難なことであることを改めて知らされた思いである。
なお、風土工学の工学は、Engineeringであろうか、Technologyであろうか。Engineeringとは、基礎科学を工業生産に応用して生産性を向上させるための応用的科学技術の総称であり、土木工学や機械工学などは、それぞれCivil Engineering、Mechanical Engineeringなどと称している。一方、Technologyは、①人生に必要なものを供給する科学的方法、②個々の技術、方法、工程、③工芸学、④専門用語などとある。Engineeringよりも幅の広い概念である。すなわち、芸術の手法や工芸などをも包含する。風土工学の場合は、以上のことよりTechnologyの方がより馴じむ概念である。
〔5〕おわりに
「ポンプ」と「風土工学」。二つの生まれの違う概念を英語と日本語でどう表記すれば良いか、考えれば考える程、日本と西洋の文化の溝の大きいことに驚かされる。